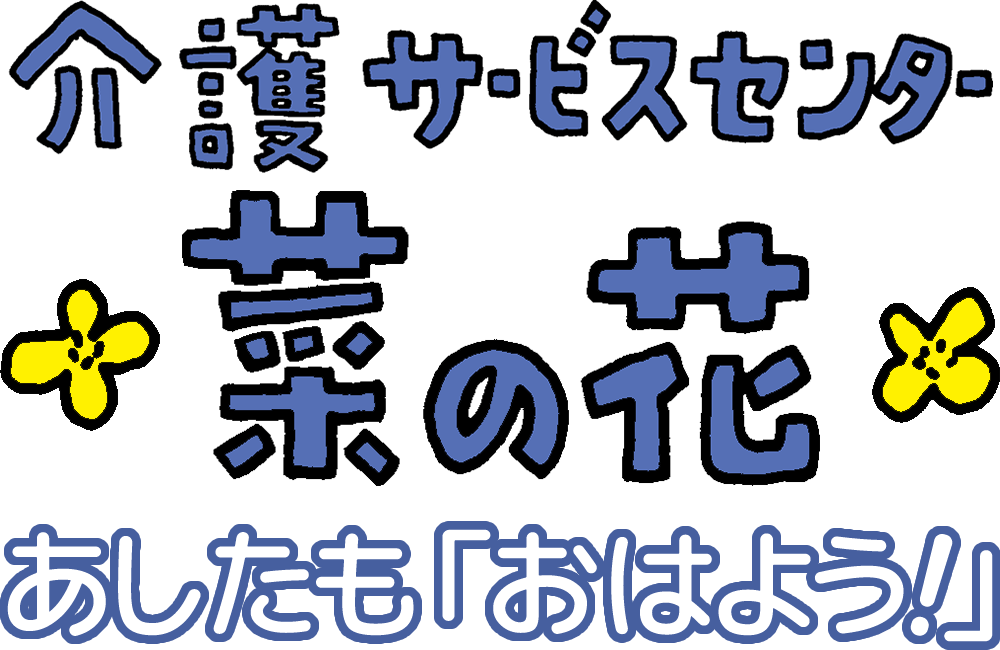今、おもうこと3月
カテゴリ名: 今おもうこと
ずいぶん古い映画になりますが、トムハンクス主演の「フォレスト・ガンプ」。大好きな映画で年に1度や2度は観ます。「 人生はチョコレートの箱、開けてみるまでわからない・・ 」というセリフから始まる物語は、反戦運動など当時のアメリカで放映された映像も混じり、同じ時代を生きてきた感覚がよみがえります。予期せぬ出来事の連続だった主人公の人生ですが、振り返ってみればすべてよい方向へ作用したようで、ドラマですが観たあといつもなにか暖かいもので満たされた気分になります。
ママが言ってた・・のセリフも随所に登場しますが、ラストシーンで、「 人には皆さだめがあり、それにしたがって生きているのか、ただ風に乗ってさまよっているだけなのか・・。たぶんその両方が同時に起こっている」とつぶやく場面があり、まさにその通りだなと感じさせられます。
少しシンドイことが起こると、まるで自分ひとりが世界中の不幸を背負ってるような気分で落ち込む。弱い人間だからこそかもしれませんが、それもこれもみな定めや巡り合わせと考えれば、荷物も少し軽くなりませんか。
たった一度きりの与えられた人生ですが、不思議なことに必要なものは全て、あらかじめ周りに用意されているのかもしれません。
自分のチカラと過信したり、棚ボタを期待して努力を怠ったり、陥りがちな遠回りに気をつけたいと思います。
どうぞお元気でお過ごしください。
丸山秀樹