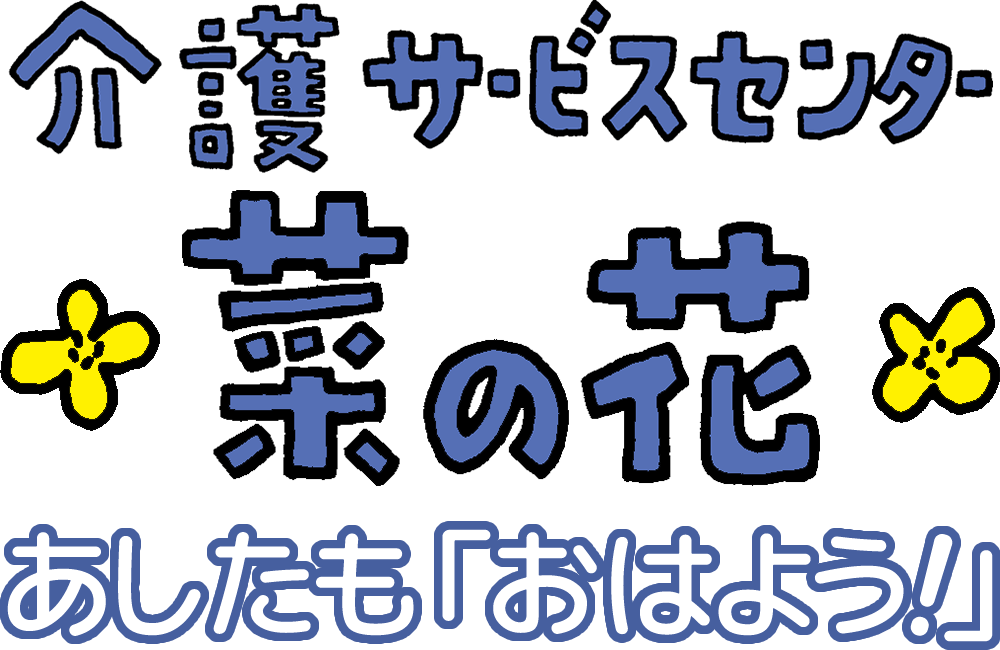その日は毎月2回開催している太極拳の日でした。
スタッフ3名のみの勤務日で少々バタバタ気味でしたが、6名の方が参加して下さり正木の家の住人さんも2名が参加しました。転倒など、怪我されないように見守り、声掛けをしながら私も一緒に参加しました。
そして毎回恒例の「おやつタイム」参加者様にも手伝ってもらいながら準備していた時、外から一人の女性が入ってこられました。
どなたかの知り合いかと思って、声をかけましたが『△#□※%!?』手には正木の家のポストに届いたであろう郵便物も・・。
それを受け取り「ポストから取って下さったんですか?」『□#△※● ・・おるんだわ!』と、中に入ってこられましたが、なぜか右足だけ裸足。
太極拳の参加者かしら?どなたか知り合いを探しているのかな?と、様子を見守りましたが、お茶とお菓子が用意された席に参加者のごとく着席されたものの、他の方と会話する様子もなく・・。
太極拳の先生に「今見えた方が居るのですがお知り合いですか?」と確認するも「ん ?! 知らないわよ・・」
もしかしたら認知症(徘徊中?)の方かしら?と、そこでやっと様子がおかしいことに気づき、近くで見守ることにしました。
会話をしても「お家は近くですか?」
『▲□%#※・・野菜なんかがあるだろ』
「買い物??」
『そうそう』 『■#△※車・・□%#▲?!』
「車はそこに止めてあるよ」
『動いとるわ!・・・うん』
あっ!道路の事?と、気づき「たくさん走ってますね~」
なかなか会話が成り立ちません。
それでも、笑顔でおやつのロールケーキはしっかり召し上がっておられました。ただ両手とも手先が「何を付けたの?!」というほど真っ黒。
太極拳参加者の方も驚かれ、話が通じないことに皆さん首をかしげていました。おやつ終了後「ヘルプー!!」と2階のスタッフを呼び、参加者様を送り出し、入居者様2名を誘導した後、急い
で110番しました。警察の方がすぐ来て下さり、捜索願が出されていないか照会してもらうと、すぐに見つかり無事に保護していただけました。 その女性のお宅は、なんと奈良県!あまりの距
離にスタッフもビックリ!
それにしても、どうやって正木まで来たんでしょう??
突然迷い込んでしまったその(おそらく認知症の)おばあちゃん。
私たち介護職員が助けることができ、迷いこんだのが正木の家で良かったと思いました。 (さくら)